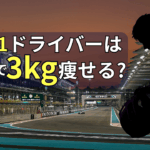AIがドリフト!?――「滑ったら危ない」が常識の世界で、あえて“滑らせて安定させる”という発想が研究されています。実は、トヨタとスタンフォードが共同研究を進め、なんと「自動ドリフト」の実験まで行っているんです。
この記事では、その狙いと仕組みをライト層にもわかる言葉でやさしく解説。先に動画で観たい方はAIがドリフト!? トヨタの“自動ドリフト”実験が凄い をどうぞ。
※実際のAIドリフト映像は記事の一番下に置いてあります。
目次(タップでジャンプ)
なにが新しい?「滑らせて安定」という逆転発想
クルマの安全はずっと「滑らせない」が正義でした。今回の研究は、どうしようもなく滑りが発生してしまった“あとの瞬間”に、車体を安定方向へ戻すため、制御された滑りを使う――という考え方です。
人間なら、逆ハン(カウンターステア)とアクセル操作の絶妙コンボ。AIは状況に応じて、必要な分だけ・すばやく操作を入れることを目指しています。
横滑り防止装置(ESC)とは?どこがちがう?
横滑り防止装置(ESC)は、カーブで外側にふくらみそうなときに、必要な車輪だけへブレーキを当てて姿勢を立て直す装置です。
いっぽう“自動ドリフト”の研究は、滑りが出たあとの体勢回復に踏み込み、ステアリング操作と駆動力の配分を使って、車体の向きを安定側へ戻すことを狙います。
ポイントは対立ではなく役割分担。横滑り防止装置が「滑らせない」ための未然対策に強いなら、“自動ドリフト”は「滑った後に最小のステップで戻す」側を強化するイメージです。
ざっくり仕組み:センサー×AIで“限界域”を扱う
クルマにはこんな情報が入っています(ざっくり):
- ヨーレート:クルマがどれくらい回頭しているか(回転の速さ)
- 舵角:ハンドル/前輪がどれだけ切れているか
- 速度:そのまま、クルマの速さ
- 横加速度(横G):カーブで横方向の力がどれだけかかっているか
- 縦加速度(縦G):加速・減速で前後方向の力がどれだけかかっているか
- スリップ率:タイヤが路面に対してどれくらい滑っているか
これらをもとに、「今の角度・速さ・路面なら、ステアを何度・駆動力をどれくらい配分すれば安定に戻せるか」を短時間で計算し、必要な分だけ操作を入れます。切りすぎ/踏みすぎを避け、最小手数で安定側へ戻すのがポイントです。
※本記事は解説目的です。公道でのドリフト走行は絶対にやめましょう。
研究の背景:TRIとスタンフォードの挑戦
TRI(Toyota Research Institute)は、アメリカにあるトヨタの研究所。パートナーはスタンフォード大学 Dynamic Design Lab(車両運動学で著名)。
両者は「プロ級の限界操作を工学的に再現する」をテーマに、スープラなど実車で、滑りの開始→維持→回復を段階的に検証してきました。ここで得られる知見は、将来のドライバー支援や自動運転の異常時バックアップに応用が期待されています。
どこに効く? 安全に近づける可能性
この研究のゴールは、公道で派手に滑ることではありません。避けられない滑りが発生した瞬間に、より安全側へ体勢を戻す“最後の引き出し”を増やすことにあります。
- 姿勢が崩れた瞬間に、被害最小化
崩れを検知→最小手数でステアと駆動力を入れて、早めに安定側へ戻す。 - 路面条件の急変(雪・氷・砂利)に強くする
「思ったより曲がらない!」状況でも、適切な角度と駆動力で踏ん張り、コース外に膨らみにくくする狙い。 - 教育/検証:匠の“感覚”をデータ化→再現
上手いドライバーの操作タイミングと量を記録→学習。運転支援のアルゴリズム洗練やドライビング教育(シミュレータ)にも波及が見込めます。
誤解しやすいポイント
- 「ドリフト推奨」ではない:研究は異常時のコントロール。公道ドリフトは危険。
- 横滑り防止装置の否定ではない:役割分担(未然対策 vs 発生後コントロール)。
- 「AIが勝手に滑らせる」わけではない:状況判断の末に必要最小限の操作を行う考え方。
まとめ
「滑らせない」に加えて、「滑っても戻す」という選択肢が増えると、クルマの安全はもう一段、厚みを持てます。研究はまだ途中段階ですが、限界域の理解と制御のデータ化が進めば、将来のドライバー支援や自動運転のバックアップは、より頼れる存在になっていくはず。
小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな安心につながる――そういうタイプの進化です。
実際のAIドリフト映像
TRI公式の実験映像です
FAQ
- Q1. もう市販車に入るの?
- A. まだ研究段階。ドライバー支援/自動運転の“異常時バックアップ”に向けた知見を積み上げ中です。
- Q2. 横滑り防止装置とどっちが優秀?
- A. 役割が違います。 横滑り防止装置は未然対策に強く、“自動ドリフト”側は発生後の最小手数コントロールに踏み込む研究です。
- Q3. ふつうの運転でも役立つの?
- A. 直接ドリフトが役立つわけではありません。限界域での体勢回復アルゴリズムが将来の安全性向上に寄与し得ます。
- Q4. 人間のプロより上手くなるの?
- A. 目的が違います。匠の操作をデータ化→再現・補完するのが狙いです。
- Q5. 練習したら公道でもできる?
- A. 絶対にダメ。 研究は管理された環境での実験。公道では安全運転一択です。